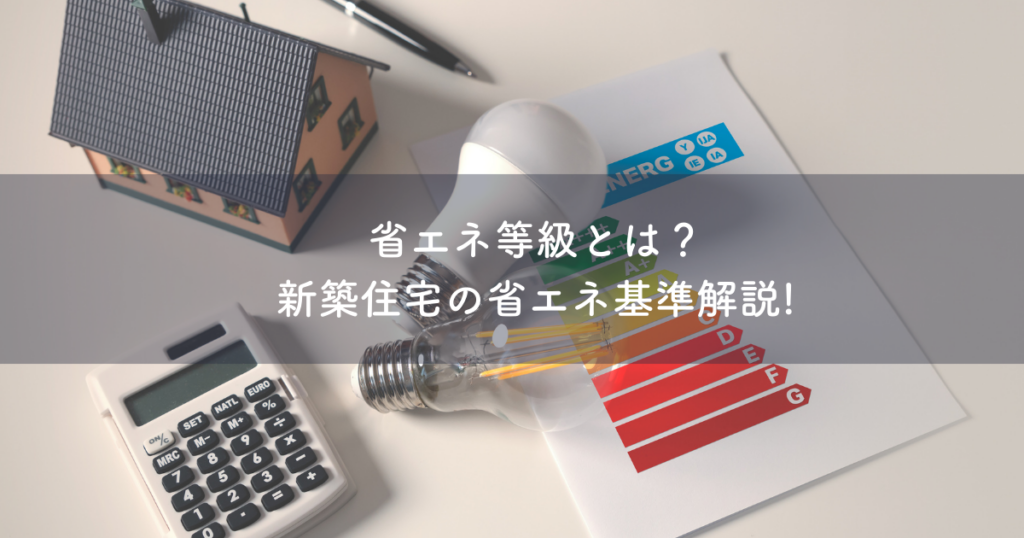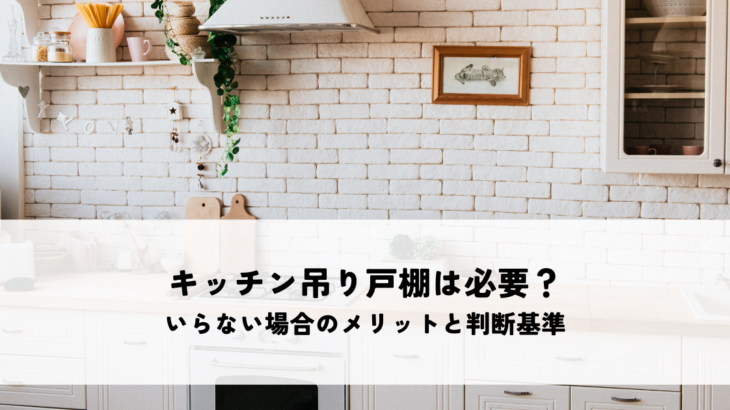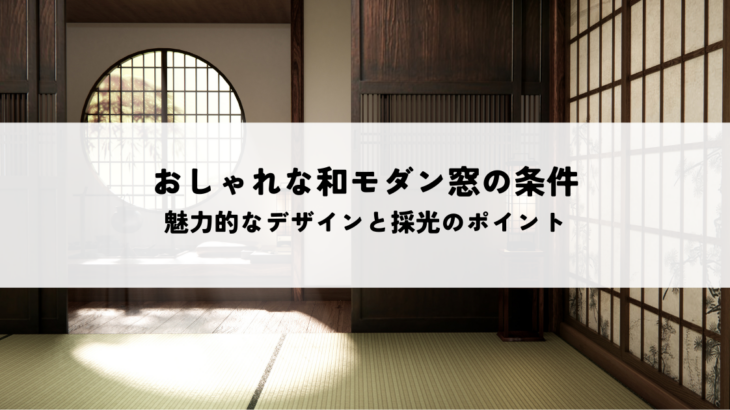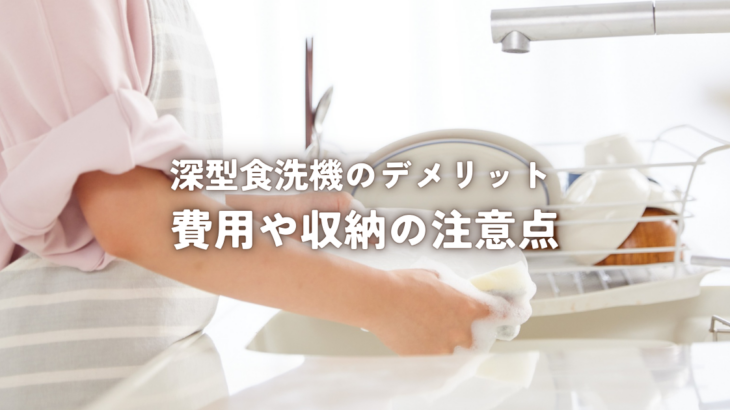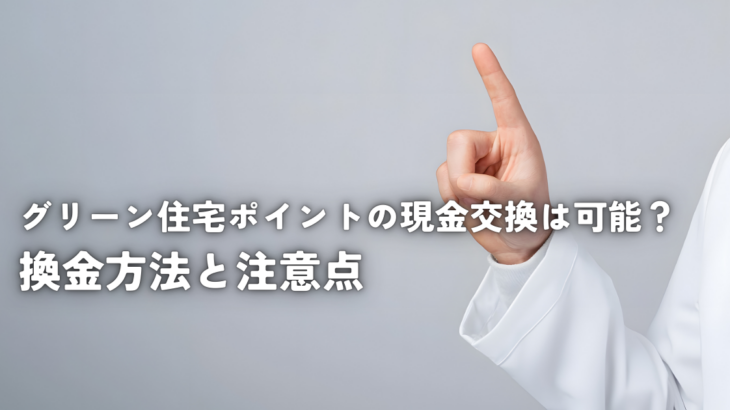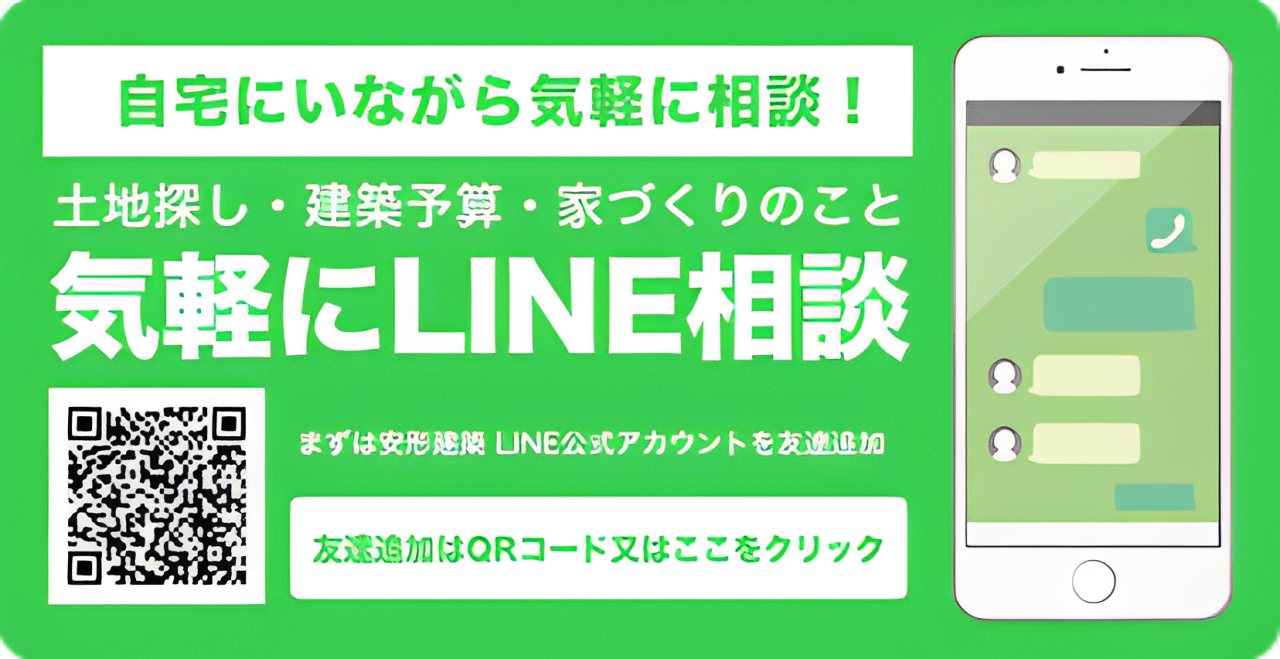新築住宅を検討する際、耳にする機会の多い「省エネ等級」。
どのようなものなのか、疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。
住宅の性能を評価する上で重要な指標であることは確かですが、その仕組みや意味を正確に理解している人は少ないかもしれません。
実は、省エネ等級にはいくつかの要素があり、近年では法改正も実施されています。
この解説を通して、省エネ等級について正しい知識を身につけて、賢い家づくりを進めていきましょう。
家を建てる皆さんにとって、役立つ情報となるはずです。
省エネ等級とは何か
省エネ等級の定義
省エネ等級とは、住宅の省エネルギー性能を表す指標です。
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づいて定められており、住宅の省エネ性能を評価する上で重要な役割を果たしています。
この等級は、住宅の断熱性能とエネルギー消費量の2つの要素から評価されます。
省エネ等級の重要性
省エネ等級は、単なる評価指標ではありません。
住宅の光熱費、居住者の快適性、そして地球環境への配慮という、家づくりにおいて非常に重要な要素に直結しています。
高い省エネ等級の住宅は、光熱費の削減、快適な室内環境の維持、そして環境への負荷軽減に繋がります。
さらに、住宅ローンや補助金制度の利用においても、省エネ等級は重要な判断材料となります。
等級制度の概要
省エネ等級は、断熱性能等級と一次エネルギー消費量等級の2つの要素によって構成されます。
それぞれの等級は1~7の数字で表され、数字が大きいほど省エネ性能が高いことを示します。
2022年の法改正により、等級制度が見直され、より高い省エネ性能が求められるようになりました。

省エネ等級の仕組みと2022年の法改正
構成要素の解説
省エネ等級を構成する2つの要素について見ていきましょう。
まず、断熱性能等級は、住宅の断熱性能の高さを表します。
断熱材や窓などの性能によって評価され、熱が逃げにくく、冷暖房効率が良い住宅ほど高い等級になります。
次に、一次エネルギー消費量等級は、住宅が1年間で消費するエネルギー量を表します。
これは、冷暖房、給湯、照明などのエネルギー消費量を総合的に評価したものです。
エネルギー消費量が少なく、省エネ性能が高い住宅ほど高い等級となります。
等級の判定基準
断熱性能等級は、建物の外皮(壁、屋根、窓など)の熱貫流率によって算出されます。
熱貫流率とは、外気温と室温の差に対する単位面積あたりの熱の移動量を表す指標です。
一次エネルギー消費量等級は、設計一次エネルギー消費量と基準一次エネルギー消費量との比率(BEI)によって判定されます。
BEIは、設計一次エネルギー消費量を基準一次エネルギー消費量で割った値で、BEIが小さいほど省エネ性能が高いことを示します。
2022年の法改正の内容
2022年の法改正では、省エネ等級の基準が厳しくなりました。
具体的には、断熱性能等級5、一次エネルギー消費量等級6が新設され、より高い省エネ性能が求められるようになりました。
また、2025年以降は、断熱性能等級4以上の住宅が義務化される予定です。
この改正は、日本の住宅における省エネ化を促進し、脱炭素社会の実現に貢献することを目的としています。

まとめ
省エネ等級は、住宅の断熱性能とエネルギー消費量を評価する重要な指標です。
高い省エネ等級は、光熱費の節約、快適な住環境、そして環境保全に繋がります。
2022年の法改正により、基準が厳しくなり、より高い省エネ性能が求められるようになりました。
新築住宅を検討する際には、省エネ等級をしっかりと理解し、自分に合った住宅を選ぶことが大切です。
省エネ等級の高い住宅は、将来的な経済的メリットと環境への貢献という、大きなメリットをもたらします。
家づくりにおいて、省エネ等級を重要な判断材料の一つとして検討することをお勧めします。
豊橋市周辺で家づくりをお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。